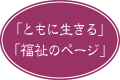
京都新聞掲載「ともに生きる」「福祉のページ」の記事をネット上で紹介するコーナーです。
|
●この人と話そう
社会全体で支える体制を
|
 |
| 母子世帯の現状についてミーティングする職員ら(京都市右京区山ノ内・野菊荘) |
私は大学を卒業してIT関連企業に就職しました。3年後に退社し、どうしようかと思っている時に、山ノ内母子寮を運営していた父の栄之から「作業員の枠が一人空いている。働かないか」と言われたのがきっかけでした。建物の修理や清掃をしていましたが、次第に福祉に関心が向いてきたので、母子支援員になりました。会社では「売り上げを拡大せよ」「利益を上げよ」と言われ続けてきたのですが、福祉の世界はまるで違います。限られたおカネの中で人々をどう幸せにしていけるかという世界です。最初はすごくカルチャーショックを受けましたね。
《母子世帯の支援は時代とともに大きく変わってきたのですか》
この野菊荘の前身は戦中の昭和17(1942)年春に開設された平安寮(後に山ノ内母子寮と改称)にさかのぼります。恩賜財団軍人援護会が設立しました。戦争で配偶者を亡くした母子の救済が始まりだったのです。その後、時代の変化によって未婚で生活困窮に陥った方や、夫と離婚または死別したが心身に障害があって就職できない方など多様化していきました。
《最近の入所者の傾向はどんな状況ですか》
DV(ドメスティックバイオレンス)から逃れて来られる母子が多くなっています。今年4月1日現在の調べですが、入所している母子世帯は30世帯で満室ですが、うち7割の21世帯が夫の暴力から逃れての入所です。DVが増加する背景は識者が分析されていますが、止める者がいない、いさめる者がいないという「密室化」のなかで弱い者に対する暴力が繰り返され、エスカレートしていくという現実があります。自分の力で解決することは難しく社会的な支援が必要です。
育児支援も実施
 |
《入所母子世帯にどんな指導や支援をされていますか》
それぞれの方が先行きに不安を持って来られるので、まずその悩みや心配を聞いて解決に向けて協力していくことが柱であり、これが最も大切なのは言うまでもありません。ほかに具体的な支援や助言を行います。自分で行うことが難しい方には、生活支援として部屋で一緒に料理をしたり、買い物に行ったり、部屋の掃除や洗濯も行うことがあります。荒れた生活の中でわが子との接し方が分からなくなるお母さんも少なくないのです。そうした方に支援員が介助すれば、大きな改善がみられます。調理指導などもします。子どもは成長していくものです。その対応がうまくいけば、子どもさんは自然と自立していくのです。こういった観点からの育児支援も行います。
《今、この分野ではどんな対策や対応が必要なのですか》
25年間、母子家庭を支援してきましたが、利用者は時代とともに変わってきました。DVから逃れてきた方が増加しているのはもちろんですが、障害者や精神疾患の方も増えてきました。家族で支え合う、親族で支え合う─などは難しくなってきています。核家族化だけでなく人間関係の希薄化もあるのでしょう。だから社会全体で支えることが必要になっているのです。全国で年間約100人の子どもが親の虐待で亡くなっているという統計があります。DVで年間約200人の女性が亡くなっているという現状があります。まだまだ支援や援助が行き渡っていないということが言えるのではないでしょうか。行政について言えば、「これだけの支援メニューがあります」と待っているのではなく、もっともっと内に入っていく努力が必要だと思います。相談体制の強化もその一つでしょう。世の中には暴力や虐待に黙って耐えている母子がいっぱいいます。
父に近づきたい
《今後の目標や夢について語って下さい》
ここに入所された母子が毎日、笑顔で過ごせるよう頑張りたいですね。精神的に不安定だったお母さんが笑顔を取り戻せば、心に大きな傷を負った子どもさんも立ち直って笑顔になります。それと目標ですが、私の父はこの母子家庭の福祉に一生をささげた人でした。自らの資産を売却し、まだ足りなくて借金に走り回ってこの施設を整備してきました。この仕事にすべてをかけていました。今年3月に亡くなりましたが、私にとって大きな存在です。父を超えるのは難しいかもしれませんが、何とか近づきたいと願っています。
せりざわ・いづる
1961年京都市生まれ。85年長野大学卒業。88年、民間企業を退社し、山ノ内母子寮に勤務。以降、母子支援員などをへて95年に母子生活支援施設「野菊荘」の施設長に就任し、現在に至る。その間、2005年には施設外にシェルター・みやこを開設しDV被害者支援に積極的に取り組む。このほか山ノ内児童館、常盤野児童館などを運営し、地域の子育て支援にも取り組む。